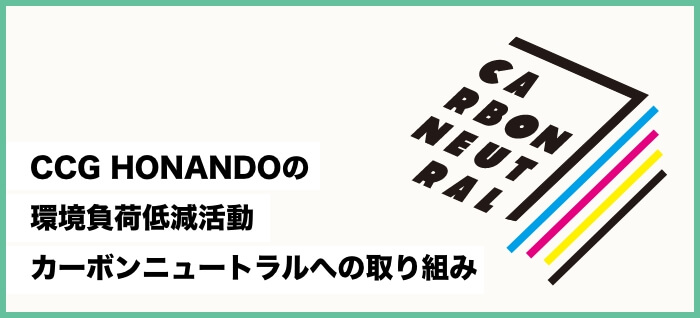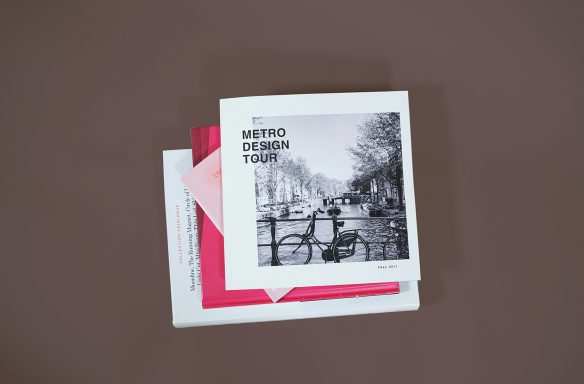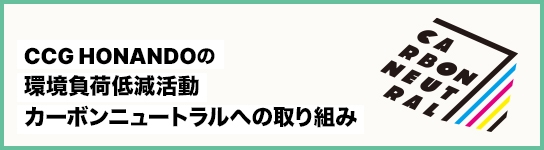2023.06.27
海洋プラスチック問題の現状と対策方法とは。問題解決につなげるCCG HONANDOの取り組み

今、世界で問題視されている海洋プラスチック問題。私たちの生活の中から出るプラスチックごみが海に流出し、海を汚染するだけではなく、そこに住む生物にも大きな影響を与えています。そして、まるで波の押し戻しのように再び私たちの元に問題として突き返されているのです。そうした海の現状がこのまま続けば、持続的に海洋資源を得ることが困難となり、経済や社会、暮らしの面でも大きな弊害になることは間違いありません。今回のコラムでは、そうした海洋プラスチック問題の全容に迫りつつ、私たち人間ができる解決策、そしてCCG HONANDOが企業としてできる取り組みについてお話しします。
〈 INDEX 〉海洋プラスチック問題とは
拡大する海洋プラスチック問題の原因
マイクロプラスチックとは
海洋プラスチックごみが与える影響
増え続ける海洋プラスチックごみの現状と予測
海洋プラスチック問題解決のために私たちにできること
海洋プラスチック問題を解決するためのCCG HONANDOの取り組み
海洋プラスチック問題の解決には身近なことから始めましょう
海洋プラスチック問題とは
海洋プラスチック問題とは、ペットボトルやビニール袋などのプラスチックごみが海に流出し、海洋汚染や生態系に影響を及ぼすことを指します。プラスチックは自然分解されないため、このまま対策をとらなければ、2050年には海洋プラスチックごみの量が魚の重量を上回ると予想されるなど、深刻な問題となっています。海洋プラスチックごみの大半は私たちの生活から流れ出たものです。プラスチックごみの流出をくい止めるには、私たち自身でアクションを起こしていく必要があるのです。
拡大する海洋プラスチック問題の原因
海洋ごみにはさまざまな種類がありますが、なかでも特に問題視されているのがプラスチックごみです。年々増え続けている海洋ごみにおいて、半分以上をプラスチックごみが占めるといわれています。その原因とされているのが、以下の3つの事項。まずは、安価で手軽に製造できるため、プラスチック生産量が増えていること。次に、手軽に使える分、手軽に捨てられてしまい、正しい廃棄処理ができていないこと。そして最後に、プラスチック自体が自然界で分解されるのに時間がかかること。この3つが、原因として考えられています。
海洋ごみ
海洋ごみとは、どのようなものが定義されているかを説明します。まずは、海岸に打ち上げられた「漂着ごみ」。そして、海面や海中を漂う「漂流ごみ」。最後に、海底に積もった「海底ごみ」。この3つを総称して海洋ごみと呼びます。「海ごみ」や「マリンデブリ」と呼ばれることもあります。今、海洋ごみの代表格ともされる使い捨てプラスチックでいえば、ペットボトルやレジ袋などが街で捨てられ、水路や川に流れ落ちて海に辿り着いてしまうことで、海洋ごみになってしまいます。このように、私たちが暮らす街から出たごみが、海洋ごみの大半を占めているのです。
化学物質の排出
海に流れ着いたプラスチックごみは、ほぼ完全に消えることはありません。プラスチックは人工的に作られた化合物のため、自然界に出ても容易に分解されることがないのです。小さなプラスチック片や細かい粒子のマイクロプラスチックとなって、世界の海を漂うことになります。これらは細かくなっても自然分解することはなく、数百年もの間、自然界に残り続けるといわれています。そもそもプラスチックは、製造の際に化学物質が添加されている場合があり、海に残留している化学物質を吸収することで、有害物質が含まれてしまう可能性も。そうしたことから、食物連鎖の最下位に位置するプランクトンが、マイクロプラスチックの影響を受けている可能性もゼロではないのです。今、食物連鎖の最上位にいる私たち人間が受ける影響においても、強く懸念されています。
マイクロプラスチックとは

5mm以下の細かい粒子になったプラスチックを、マイクロプラスチックといいます。丈夫で加工しやすく、安価に製造可能なプラスチックは世界でさまざまな製品として流通しています。手軽に入手できるというメリットがある反面、手軽に捨てられてしまうことが懸念点。海に流れ着いたプラスチックは、小さくなったとしても自然界の中で分解されることはありません。このマイクロプラスチックによって引き起こされる環境問題が、マイクロプラスチック問題です。ここでは、大きく分けて2種類あるマイクロプラスチックについて説明します。
一次マイクロプラスチック
一次マイクロプラスチックとは、製品や製品原料として使用する目的のために作られた、微小なサイズのプラスチック。つまり「元から小さく作られたプラスチック」のことです。プラスチックの原料となるレジンペレットもサイズによってはマイクロプラスチックに分類されます。身近なもので挙げると、洗顔料や歯磨き粉に含まれるスクラブ剤。研磨剤として小さく加工されたプラスチックが使用されるケースがあり、それは生活排水と一緒に流されているのです。
二次マイクロプラスチック
二次マイクロプラスチックとは、プラスチック製品が自然環境の中で劣化し、粉々になったことで生じたマイクロプラスチックを指します。つまり「元々は大きかったが、摩耗することで小さくなった破片」のことです。海洋ごみとして流出したペットボトルやレジ袋などのプラスチック製品が、時間の経過とともに雨風や紫外線にさらされ、粉々になることで発生するケースが多いと考えられています。
海洋プラスチックごみが与える影響
プラスチックは手軽で耐久性があり、安価に生産できることから、製品そのものだけでなく、ビニールや発泡スチロールといった包装や梱包など、生活のあらゆる場面でも使用されています。プラスチックは便利な一方で、適切に処理されないと下水や河川などから海に流出し、海の生態系や人間の人体に影響を与えます。ここでは、それぞれの影響について説明します。
生態系に与える影響

分解されない海洋プラスチックごみは、海に住む魚類、海洋哺乳類、鳥類などの生態系に影響を及ぼしています。その一例が「ゴーストネット」と呼ばれる廃棄された漁網。幽霊のように海中を漂い、魚を含めた海洋生物を絡め続けることからそのように呼ばれています。プラスチック製の漁網は長持ちするように作られており、漁業網に絡まったクジラや海鳥が窒息死することも。また、ウミガメやアザラシが海に漂うビニール袋を餌と勘違いして食べてしまう事例も報告されるなど、多くの生物がプラスチックごみによって犠牲になっています。
人体に与える影響
マイクロプラスチックは、人体にも影響を及ぼします。マイクロプラスチックは5mm以下と非常に小さく、小魚やプランクトンが餌と間違えて食べてしまうこともあります。マイクロプラスチックが魚の体内に蓄積されることで、食物連鎖を通じて生態系のより上位の人間の体に取り込まれる危険性があるのです。人体への影響ははっきりと解明されていませんが、1週間でクレジットカード1枚分に相当する5gのプラスチックを摂取していると言われています。
増え続ける海洋プラスチックごみの現状と予測
2019年の使い捨てプラスチックの廃棄量は、世界全体で1億3,000万トンにものぼります。そのうち、日本は471トンで4位となっています。また、世界全体で1950年以降に生産されたプラスチック量は83億トンを超え、63億トンがゴミとして廃棄されていることもわかりました。回収されたプラスチックごみの79%が埋め立てや投棄されており、リサイクルされているものはわずか9%にしか過ぎません。前述の通り、投棄されたプラスチックごみが河川から海に流れ着くことで、海には多大な影響を与えているのです。現状のペースで考えた時、2050年までに120億トン以上のプラスチックごみが埋め立て・自然投棄される予測が出ています。それは、非常に恐ろしいことではないでしょうか。
海洋プラスチック問題の解決のためにできること
これまで海洋プラスチック問題について説明してきましたが、解決するためにできることはどんなことがあるでしょうか。国家規模での取り組みはもちろんですが、個人でもできる解決の糸口について説明していきます。
基本の3Rを意識する
海洋プラスチックごみに関わらず、ごみ問題の解決に必要なことは基本の3Rです。
・リデュース(Reduce)=物を大切に使い、ごみを減らすこと
・リユース(Reuse)=使える物は、繰り返し使うこと
・リサイクル(Recycle)=ごみを資源として再び利用すること
この3Rを徹底することが、問題解決につながる一番の近道です。日本国内では、廃棄されたプラスチックの有効利用率が84%程度あり、特に進んでいるといわれていますが、全体の約58%は「サーマルリサイクル」という方法に頼っています。サーマルリサイクルとは、主にプラスチックを焼却した時の熱エネルギーを再利用するリサイクル方法。しかし、プラスチック自体をリサイクルしているわけではないため、海外ではリサイクルの一種には含まれていません。やはり、根本的な使用量を減らすことが何よりの解決策です。
近年、「3R」の前にリジェクト(Reject)やリフューズ(Refuse)=ごみになるものを買わずに拒否することを加えた「4R」という考え方も見られます。例えば、スーパーで肉や魚を買う際にプラスチックの使い捨てトレーがついてきますが、トレーを受け取らずに買う方法もあるはずです。Rの「入口」からごみになるものを受け取らないという態度を示すことで、プラスチックごみの量は大量に減らせるでしょう。
プラスチックごみの無駄な消費を減らす
日本国内におけるペットボトルの年間出荷量は230億本にのぼりますが、リサイクルされるのは約90%。リサイクルされなかったペットボトルは、ゴミとして捨てられていたり、ポイ捨てされていたりする可能性があります。まずは、なにげなく投棄したペットボトルが、海洋プラスチックごみを増加させる要因につながることを理解しましょう。プラスチックごみの無駄な消費を減らすためにはペットボトルをマイボトルに変える、レジ袋をエコバックにする、詰め替え可能な洗剤を使う、目の細かい洗濯ネットを利用して洗濯時のマイクロファイバーの流出を軽減するなど、日々の暮らしを見直すことが消費者としてできる行動の第一歩。プラスチックごみの無駄な消費を減らして、海洋プラスチックごみを根本から減らしていきましょう。
ごみ拾い・清掃活動に参加する
増え続ける海洋プラスチックごみを減らすには、私たち一人ひとりの意識の変化が大切です。基本の3Rを意識しながら、購入したものは大切に使ってごみを減らす、壊れた製品は直しながら繰り返し使う、資源として再利用する……こうした取り組みを積極的に行なっていくことで、プラスチックごみを少しずつ減らせるでしょう。また、街中や河川、ビーチのごみ拾い・清掃活動のボランティアに参加することもおすすめです。ごみが海に流出する前に処理することで、海の生態系の維持に貢献できますし、日常生活でどれくらいの量のごみが出ているのかを知るきっかけにもなります。ごみ拾い・清掃活動のボランティア活動は全国各地で開催されているため、活用してみましょう。一人ひとりが行動を変えれば、海洋プラスチック問題の解決に、ひいては自分自身を守ることにつながります。まずは、無理なくできることから始めてみませんか。
海洋プラスチック問題を解決するためのCCG HONANDOの取り組み
CCG HONANDOでは、世界的な海洋プラスチック問題を重く受け止め、解決へとつなげるための新たな自社製品を作っています。
ペーパーファイル

プラスチック製品の多い日本では、プラスチック製品を他の素材に代替することで、リデュース(プラスチックごみを減らす)につなげることも重要です。例えば、営業活動で使用しているプラスチック製のクリアファイル。得意先への資料送付や、展示会での資料配布など、その場限りで使用されるケースが多いと思います。また、最も多く使用されているのは、契約を伴うカウンター業務ではないでしょうか。プラスチック製のクリアファイルでは、契約書類を持ち帰った後にリサイクルすることはできません。これを紙製のファイルに変えるだけで、リサイクルが可能になります。プラスチック製のクリアファイルと違って中が見えないので、個人情報の取り扱いにも有効。オリジナルで作成することもできるので、例えば抗菌印刷にしたり、FSC認証紙を使用したり、より一層環境に配慮した仕上がりにすることも可能です。ラインナップとして、無地のペーパーファイルもご用意しています。オンデマンド機で必要部数だけ印刷することができるため、安価に製作でき、ロスが減らせるというメリットもあります。
紙製うちわ

一般的なうちわには、プラスチック製の持ち手が付いています。プラスチック製の持ち手が付いていると、やはりリサイクルができません。しかし、円形の紙製うちわにすることで、リサイクルが可能となるのです。また、すべて紙で作られたものなので、コンパクトに持ち歩くことが可能。いつも使っているアイテムの素材を変えるだけで、環境に配慮でき、海洋プラスチック問題の解決につながる取り組みになります。
CCG HONANDOは海洋プラスチック問題の解決策となる製品をはじめ、環境に配慮した製品を多数揃えています。お客様のご要望に合わせてご提案いたしますので、いつでも気軽にお問い合わせください。
海洋プラスチック問題の解決には身近なことから始めましょう
環境省の調べによれば、毎年800万トンのプラスチックごみが海洋に流出しているという試算があります。このままのペースで流出が続くと、2050年には海洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超えてしまう、という予測も発表されているほど。ですが、プラスチックは加工も容易で、安価に使用できる素材です。強度もあるので、必要なものとして使われているケースも多く見受けられます。そのため、「脱」プラスチックという取り組みはすぐに始めることは難しいかもしれませんが、まずは身近なものから、「減」プラスチックに取り組んでみてはいかがでしょうか。CCG HONANDOでは、紙製のファイル「ペーパーファイル」や、紙だけでできた「紙製うちわ」など、減プラスチックに手軽に取り組めるアイテムを多数取り扱っています。サンプルもご用意していますので、気軽にお問い合わせください。
Contact
各種お問い合わせ / 印刷のお見積もり・ご相談など
ご不明点ございましたらこちらよりお問い合わせくださいませ