
中綴じとは?ページ数の少ない冊子印刷に最適な製本方法
一枚一枚の印刷物を冊子に仕上げる製本にはいくつもの種類があります。今回クローズアップする「中綴じ」は、週刊誌や情報誌などによく使われ、皆さんにとても馴染みがある製本方法です。そこで、中綴じのメリットやデメリットをはじめ、冊子を印刷する時に役立つ情報をお届けします。
2021.02.16
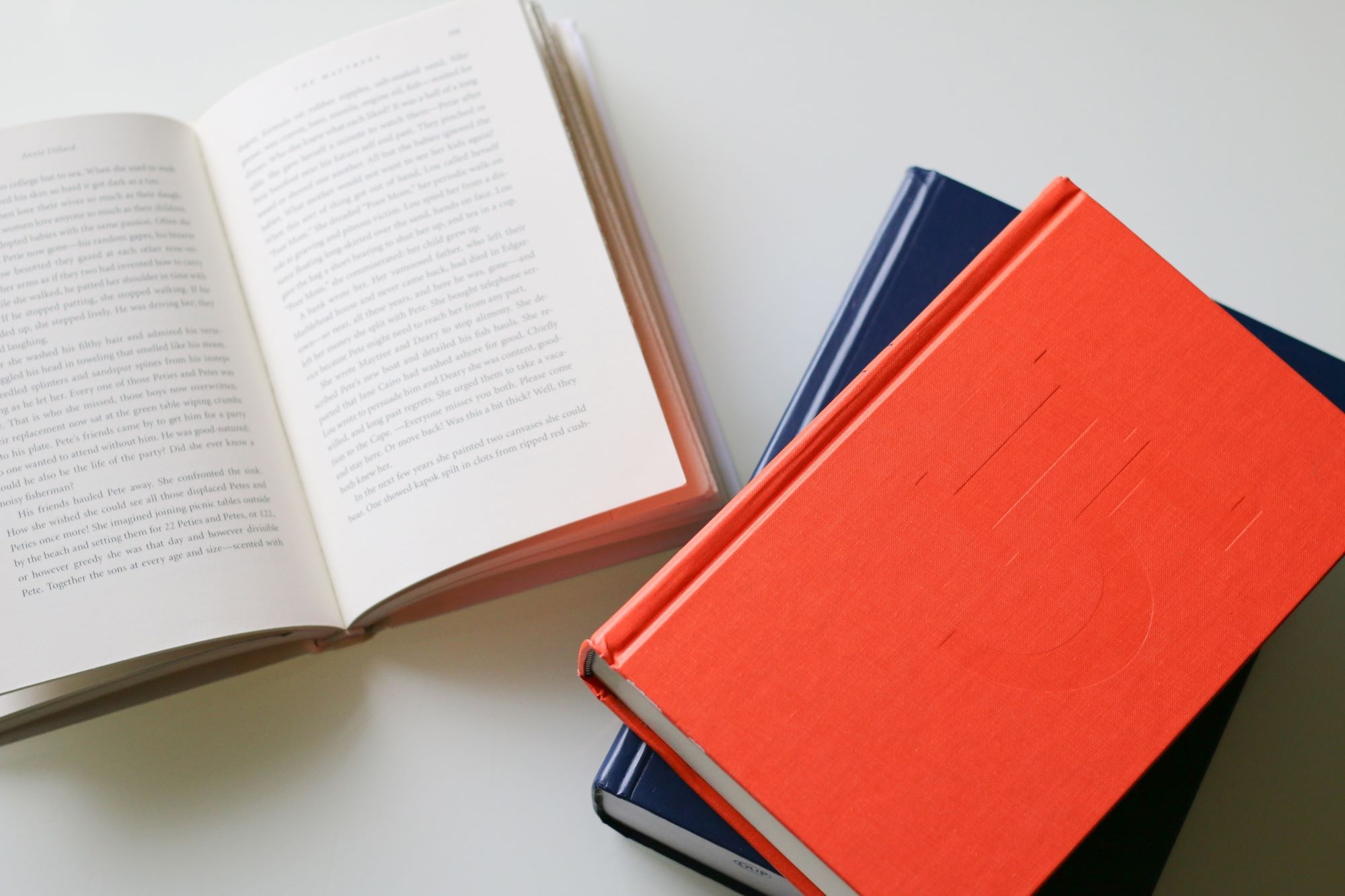
これまで、中綴じや無線綴じ、あじろ綴じといったいろいろな製本方法をご紹介してきました。今回ピックアップするのは「上製本」。別名ハードカバーとも呼ばれ、卒業アルバムや写真集などに採用されている製本方法といえば、想像しやすいのではないでしょうか。本コラムでは、そんな上製本の特徴やメリットなどをお伝えします。
〈 INDEX 〉複数枚の印刷物をまとめて表紙をつけ、本に仕立てることを製本といいます。製本には、上製本や並製本や、リング製本といった種類があり、綴じ方の違いによって呼び方が変わります。ページ数はどのくらいなのか、どんな目的で使用するのかなど、仕様に合わせてさまざまな方法を選ぶことができます。
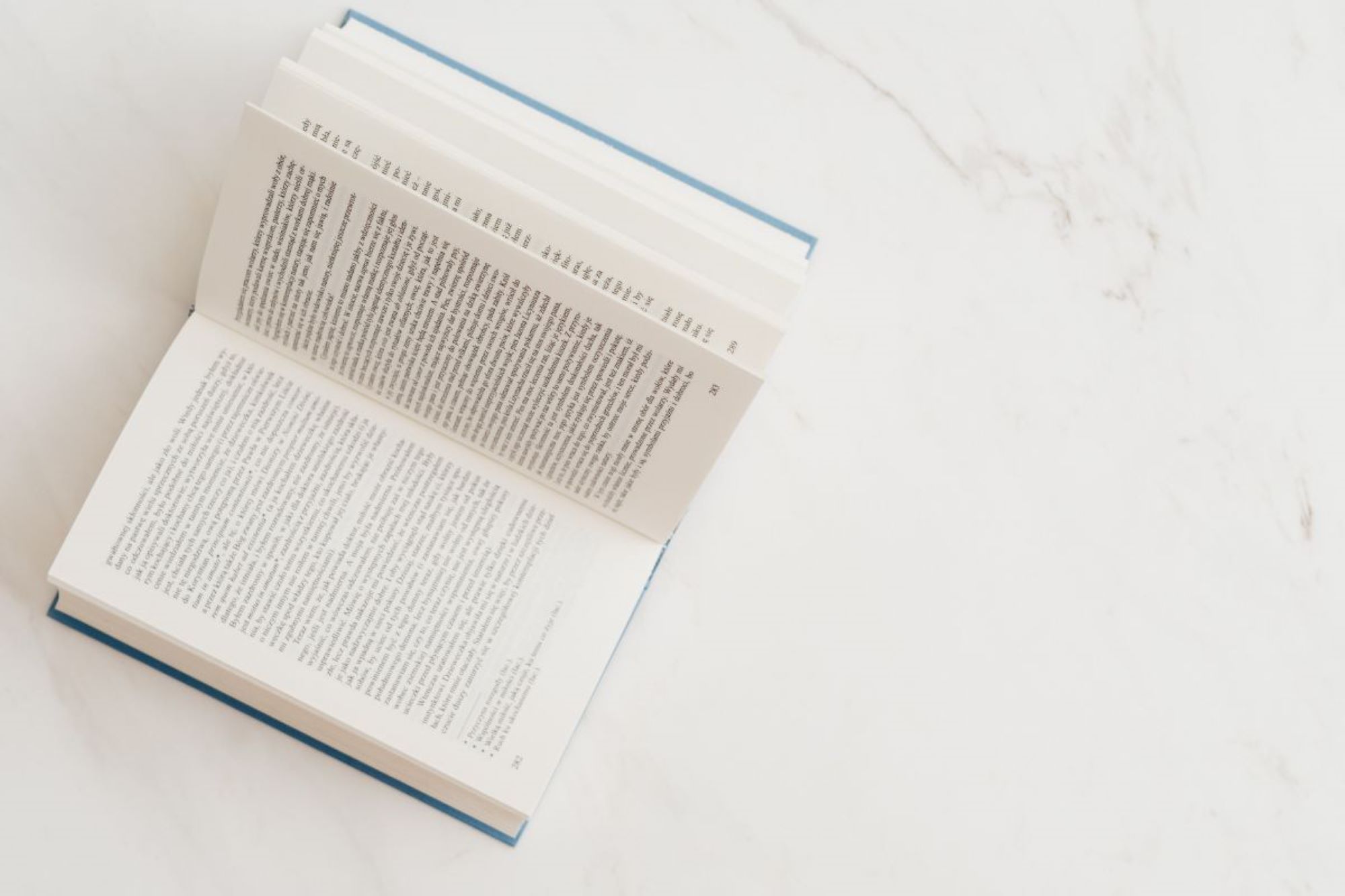
上製本とは、いわゆる「ハードカバー」で作られた本のことを指します。本の中身を専用の糸や接着剤で綴じ、中身とは別で仕立てた硬くて厚い表紙で包むため、とても頑丈です。外部からの衝撃に強く、長期保存に向いているため、パンフレットのような多数配布するようなものではなく、記念となる特別な冊子に採用されることが多い製本方法です。上製本は手作業で製作する部分が多く、中綴じや無線綴じといった並製本よりも、費用・日数ともにかかります。
ひと口に「上製本」といっても、その種類はさまざまです。例えば、本文の綴じ方にしても、「糸かがり綴じ」「あじろ綴じ」「中ミシン綴じ」などがあります。そのほか、背の部分を丸く綴じた「丸背」、四角く綴じた「角背」があり、仕上がりのイメージに影響を与えます。
仕上がりのイメージが変わるという点では、表紙の素材が豊富なのも上製本の特徴です。上製本では、表紙を本文とは別に仕立てます。そのため、普通の印刷用紙のほかに、布クロスやレザークロスを使うことができ、より高級感を出すことが可能になります。
上製本は、さまざまな商品に使用されています。身近なところでは、絵本や卒業アルバム、会報誌や記念誌などがあります。そのほか、少し特別感のあるノベルティとしてノートや手帳などに採用されることもあります。周年記念ノベルティやお得意様向けノベルティなど、高級感が求められる商品に使われています。
上製本のほかに、「並製本」という製本方法があります。並製本は、針金や接着剤などで綴じた冊子全般を指し、綴じ方によって「中綴じ」「無線綴じ」「平綴じ」などがあります。
●中綴じ…見開きのページを2つ折りにして、真ん中を針金で留めた製本 ●無線綴じ…本文の束を表紙で包み、背を製本用の特殊糊で綴じた製本 ●平綴じ…単ページを束ねて針金で留めた製本
並製本は、上製本と比べると短い納期かつ安い価格で製作できるのが大きなメリットです。一般的に目にする機会が多いのは並製本で、小説やビジネス書などの文庫本、雑誌やカタログ、マンガ本といった商業印刷から、会社案内やカタログをはじめとするビジネス向けの資料などに採用されています。

一枚一枚の印刷物を冊子に仕上げる製本にはいくつもの種類があります。今回クローズアップする「中綴じ」は、週刊誌や情報誌などによく使われ、皆さんにとても馴染みがある製本方法です。そこで、中綴じのメリットやデメリットをはじめ、冊子を印刷する時に役立つ情報をお届けします。
上製本は、中綴じや無線綴じなどの並製本と比べて製本の流れが複雑なため、費用と日数がかかります。しかし、ハードカバーを使って製本することで、耐久性に優れ長期保存に最適な冊子に仕上げることができます。また、表紙をはじめとする装飾の工夫によって、同じ内容でもまったく違うイメージの本になります。ここでは、保存性の高さや仕上がりの美しさ、加工方法のバリエーションなど、上製本ならではの特徴を詳しくご紹介します。
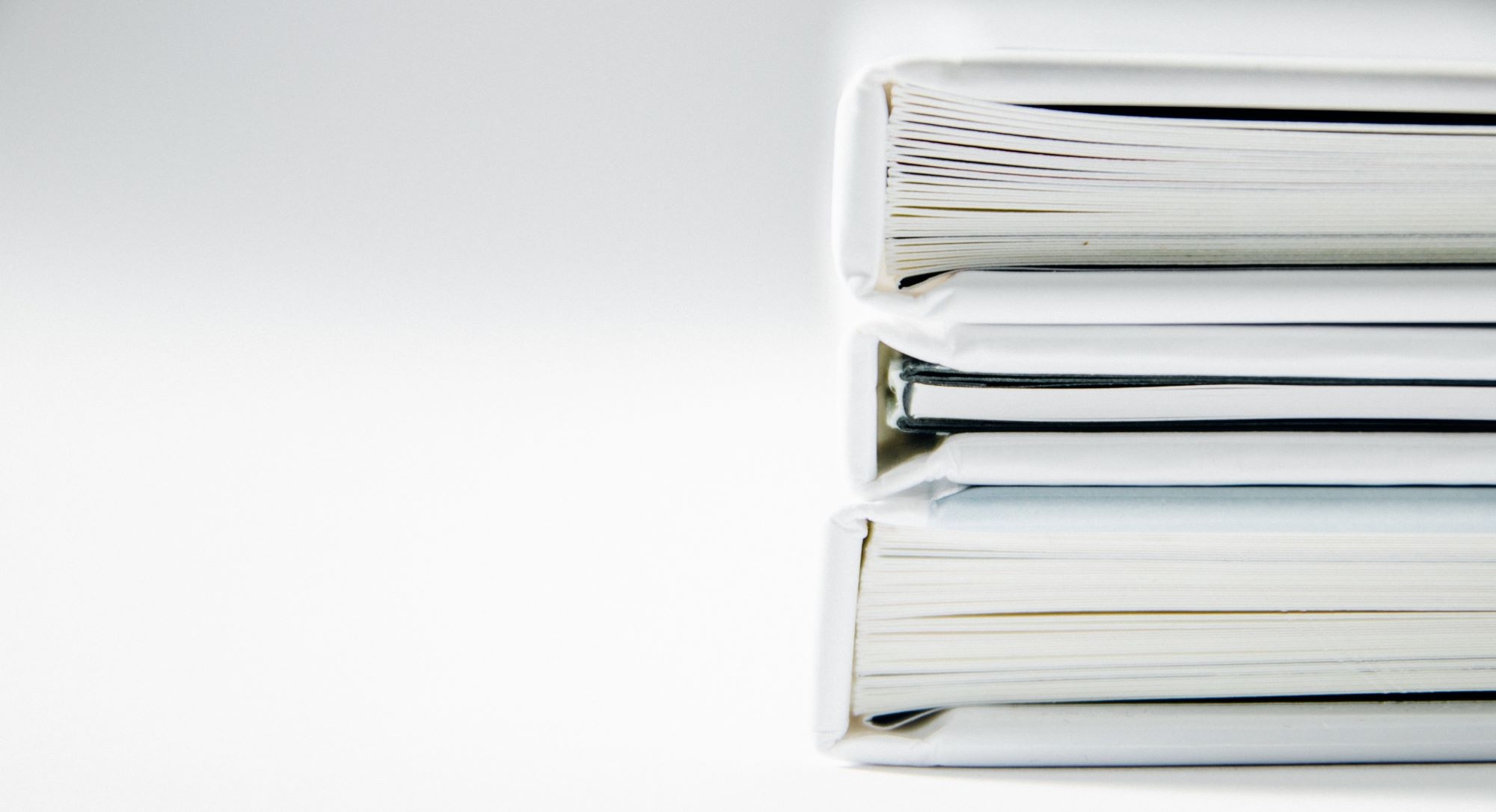
上製本は、糊や糸などで綴じた本を、別で仕立てた厚めの表紙で包みます。そのため耐久性が高く、長期保管に耐えられる仕様になっています。表紙の硬く分厚い芯の部分は「芯材」と呼ばれるボール紙を使用しています。表紙にボール紙を使用することで、より頑丈で長期保管できる本に仕上げることができるのです。
また、上製本の本文の製本方法としてよく使用される糸かがり綴じは、強度が強く、大きく開いてもページが脱落しにくいのがメリット。卒業アルバムや記念誌、学術誌や絵本など、長期保管が求められる冊子に採用されているのは、この耐久性の高さゆえなのです。
上製本は、本文とは別に用意した表紙で包む製本方法です。そのため、通常の中綴じや無線綴じとは違い、布クロスやレザークロスなどの素材を表紙として選ぶことができます。さまざまな色の中から冊子のイメージに合った色味や素材を選ぶことによって、見た目の重厚感や独特の手ざわりが生まれ、本を手に取った時に特別感を与えてくれます。さらに、紙ではなく布やレザーを使うことで耐久性もアップ。用途や目的に合わせてさまざまなご提案が可能ですので、ぜひご相談ください。
上製本は、表紙と本文を別工程で作ります。本文に貼り込んだ見返しの片側前面に接着剤を塗布し、表紙の裏面に貼り合わせることで表紙と本文を接合。そのため、上製本の巻頭と巻末に必ず見返しが付いています。また、上製本の背の形状は、本の目的に合わせて3種類の形から選ぶことができます。
●ホローバック(腔背)…背が空洞で本の開閉がしやすい ●タイトルバック(硬背)…本の中身と表紙の背を密着させるため、丈夫な反面やや開きにくい ●フレキシブルバック(柔軟背)…薄表紙の辞書類に用いられる。背文字の箔が落ちやすい
ほかにも、「花布(はなぎれ)」と呼ばれる本の中身の天地両端に貼り付ける小さい布や、しおりのような役目をする「スピン」など、オプションの選択肢が多く、こだわりの1冊に仕上げられるのも上製本ならではの特徴です。
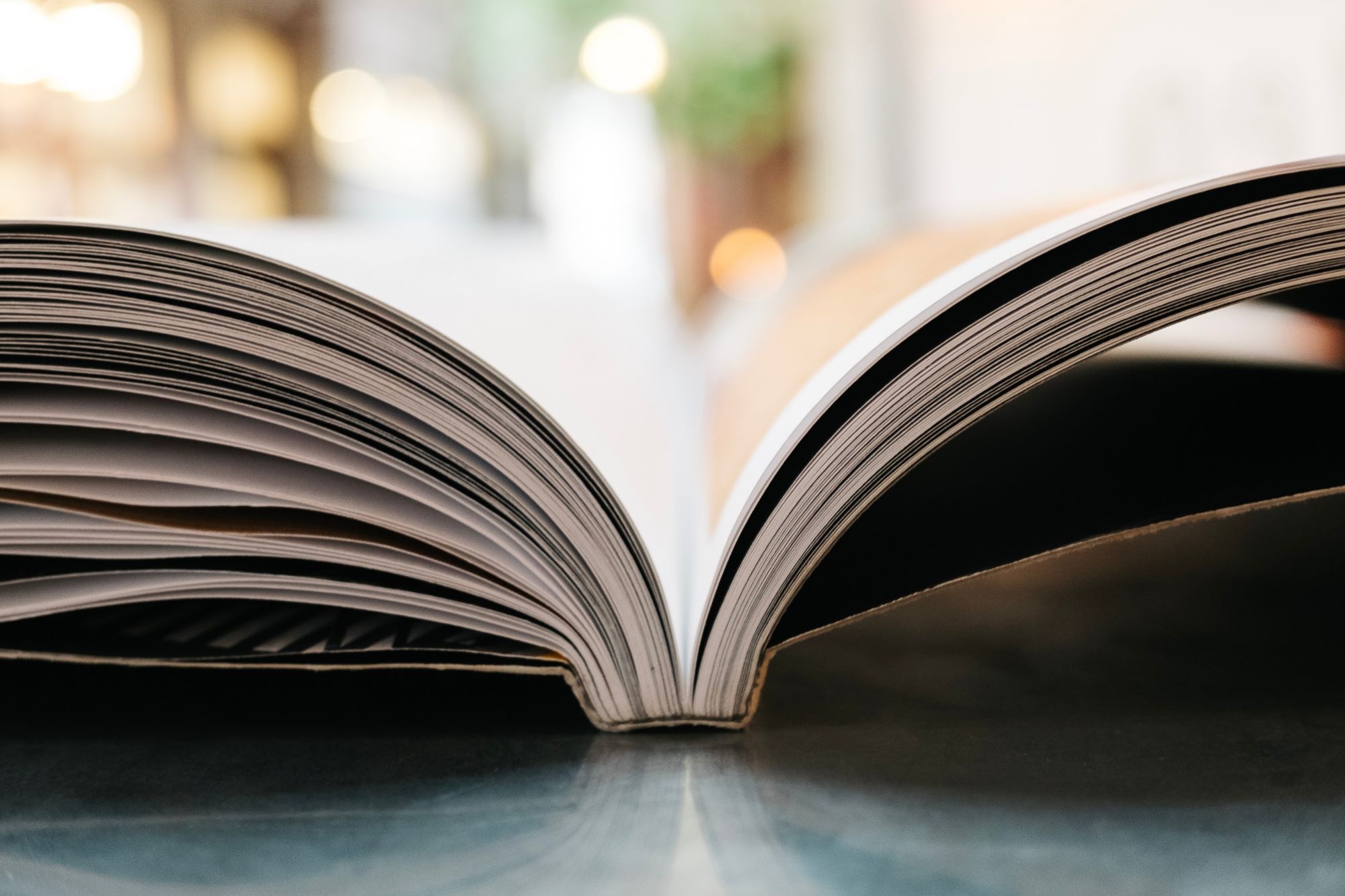
上製本では、表紙と本文のサイズが異なります。それは、「チリ」と呼ばれる表紙のはみ出し部分があるからです。基本的には、表紙が本文よりも2~3mm程度大きい設計になっています。また、表紙は芯材と呼ばれるボール紙を包むため、15mm程度伸ばしてデザインをする必要があります。
このように、並製本では特に気にしなくても問題ないようなポイントに注意してデザインを制作する必要があります。ページ数によって背幅や空きが変わるため、デザインを制作する際は、事前にお問い合わせいただくと安心です。
また、ページ数の多い製本の場合、「ノド」と呼ばれる本を開いたときに中央になる部分にも注意が必要です。通常の中綴じと同じようにデザインをすると、ノドの付近の文字が読めなくなったり、絵柄が見えなくなったりする可能性があります。そのため、原稿やデザインのデータを入稿する時は、余白部分に注意を払わなければなりません。
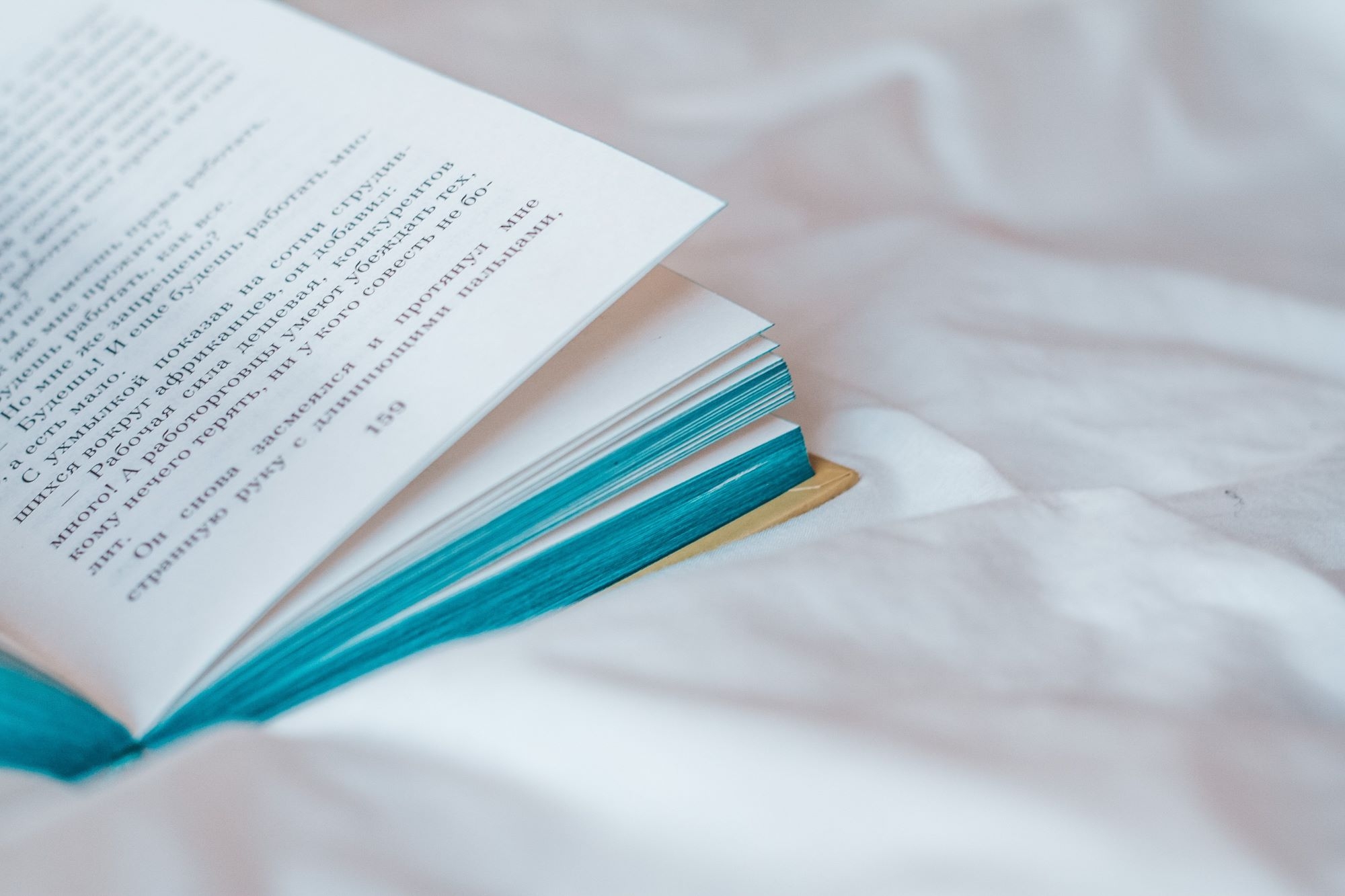
納得のいく上製本を作るうえで、発注時におさえておきたいポイントがあります。前述の通り、表紙の素材や背の形状、花布やスピンなど、通常の並製本と違い、自分のこだわりを詰め込めるのが上製本の特徴です。また、用紙を決める時には、以下の3つのポイントに留意してみてください。いずれも選ぶ素材によって仕上がりのイメージが多く変わります。
①本のイメージを決める表紙素材の選び方 ②用途に合わせた本文用紙の選び方 ③雰囲気を左右する見返し用紙の選び方
上製本は並製本に比べ、用紙の選択肢が多い製本方法です。選び方のポイントや具体例をまじえて詳しくご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
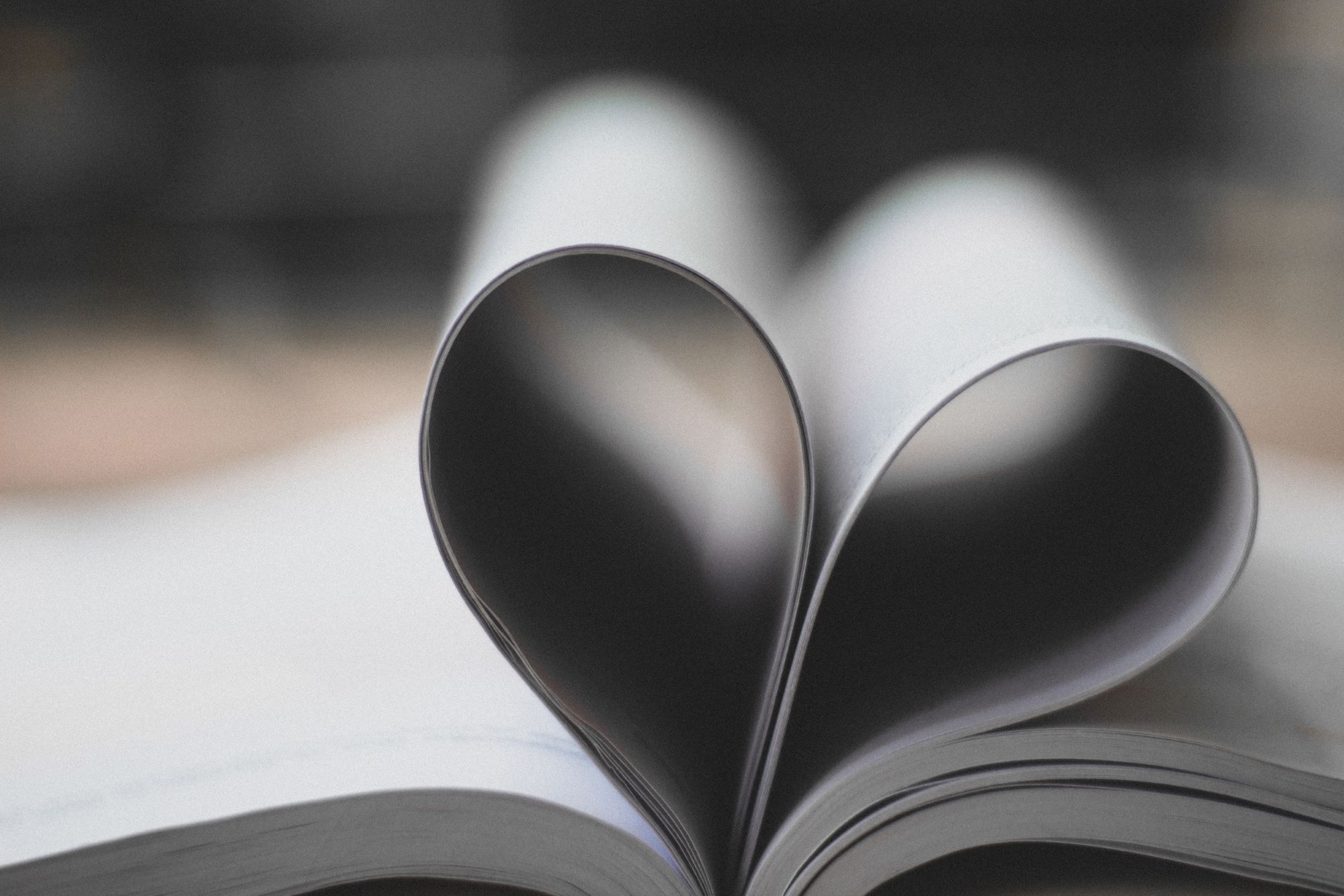
上製本では、さまざまな素材を表紙に使用できます。普通の印刷用紙はもちろん、布クロスや細布、麻布、レザークロス、ビニールクロスなど、さまざまな種類からお選びいただけます。フルカラー印刷が可能なものから、素材感を活かして箔押しやシルク印刷のみの加工に適しているものまで、イメージに合わせてお選びいただけます。冊子の目的や仕上がりのイメージを事前に明確にしておくことが大切です。
用途や仕上がりのイメージに合わせて、本文用紙もお好みのものを選びましょう。写真の発色に適した用紙、耐久性を重視した厚めの用紙、そして高級感のあるファンシーペーパーなど、選択肢はさまざまです。例えば、ノートとして使用するなら、「上質紙」や「書籍用紙」といった筆記特性の高い用紙、「クリーム上質」のように目にやさしい用紙を選ぶのがおすすめ。ほかにも、印刷する内容やデザインによってご提案の幅は広がります。
見返し用紙とは、表紙・裏表紙と本文を接合するための紙のこと。本文の最初と最後に付けられ、上製本では必須のパーツであり、強度や高級感が増す大事なポイントでもあります。色上質紙を使用したり、本文と違う色や質感の用紙を使用したり、選ぶ紙によって特別感を出すことができます。たった1枚の紙ですが、仕上がりのイメージや印象が大きく変わるため、ぜひこだわりたいポイントです。
本や冊子には、主に「右綴じ」「左綴じ」といわれる綴じ方があります。冊子を表紙側から見た時、右側で綴じられている綴じ方が「右綴じ」、左側で綴じられている綴じ方が「左綴じ」です。
同じ意味合いで、「右開き」「左開き」といわれることもあります。「右綴じ」か「左綴じ」かは、通常は文字を読む方向によって決まっています。縦書きの場合は「右綴じ」、横書きの場合は「左綴じ」となります。「右綴じ」は、主に国語の教科書や文庫本で使用されており、「左綴じ」は主に数学や英語の教科書、楽譜などで使用されています。また、文章よりも写真やイラストなどが多い場合も、本文が縦書きであれば右綴じにします。
今回のコラムでは、上製本の特徴やメリットなどをお伝えしてきました。用途や仕様に合わせて製本方法を選ぶことが、製品のより良い仕上がりにつながります。
例えば、学校案内やパンフレットなどたくさんの人に見てもらいたい冊子を作る時、上製本はコストやスケジュールの面から適しているとはいえません。このような冊子の場合は、表紙と本文を2つに折ったものを重ね、真ん中をホチキスや針金で留める「中綴じ」がおすすめです。中綴じは定番の製本方法で、コストが抑えられるのが最大のメリットです。しかし、ホチキスや針金で留めるため、ページ数が多い製本に向いていないのが難点です。
ページ数が多い場合は、背にあたる部分に切り込みを入れ、製本用の強力な接着剤を使って製本する「無線綴じ」や「あじろ綴じ」の製本方法がおすすめです。それぞれの違いをご説明しますので、製本方法を選ぶ時の参考にしてください。

無線綴じは、糸や針金を使わず、製本用の強力な接着材(ホットメルト)を使う綴じ方法です。ページを1枚ごとにバラバラに切り離し、露出した紙の断面に接着剤を塗布して背を固めます。紙が薄いと接着剤が十分に浸透しない可能性があるため、無線綴じがおすすめです。
冊子の製本方法には、「中綴じ」や「糸綴じ」などいくつもの綴じ方がありますが、今回は「無線綴じ(くるみ製本、くるみ綴じ)」をピックアップ。無線綴じは、文庫本や参考書、カタログといったさまざまな冊子に使用されている製本方法で、皆さんがお持ちの本をはじめ、書店でも見かけたことがあると思います。そんな無線綴じの特徴からメリット・デメリットまで詳しく解説します
無線綴じ(くるみ製本)とは?特徴や中綴じとの違い、メリット・デメリットを詳しく解説
あじろ綴じは、無線綴じを改良した製本方法です。無線綴じと同様に、製本用の強力な接着剤で背を固めて製本します。本文を1枚ごとにバラバラに切り離してから背を固める無線綴じと違い、あじろ綴じは8ページや16ページごとに折丁(おりちょう)を作るのがポイント。その際、ページを切り離さずに背の部分に切り込みを入れ、つなぎ部分を残したまま接着剤を塗布して背を固めます。4/6判110㎏のような厚めの紙を使う場合には、背割れを起こしやすくなるため、あじろ綴じがおすすめです。

冊子の製本方法には、「中綴じ」や「糸綴じ」などいくつもの綴じ方がありますが、今回は「無線綴じ(くるみ製本、くるみ綴じ)」をピックアップ。無線綴じは、文庫本や参考書、カタログといったさまざまな冊子に使用されている製本方法で、皆さんがお持ちの本をはじめ、書店でも見かけたことがあると思います。そんな無線綴じの特徴からメリット・デメリットまで詳しく解説します。
このように、同じような仕上がりに見えても、実は用紙や仕様によって綴じ方を変えていることがあります。ほかに、伝統的な上製本の綴じ方で、糸を使って本文を綴じる「糸かがり綴じ」という方法もあります。
近年は、製本技術や接着剤が改良されたことによって、無線綴じやあじろ綴じの製本方法が普及していますが、糸かがり綴じもまだまだ使われています。糸かがり綴じの特徴は強度にあり、大きく開いてもページが脱落しないことがメリットです。ページを大きく開きたい場合や厚い本文用紙を使用したい場合は、糸かがり綴じがおすすめ。例えば、アルバムや日記など長期保管したいものに適しています。ただし、ほかの製本方法に比べると、製作工程が多く、日数やコストがかかるというデメリットもあります。
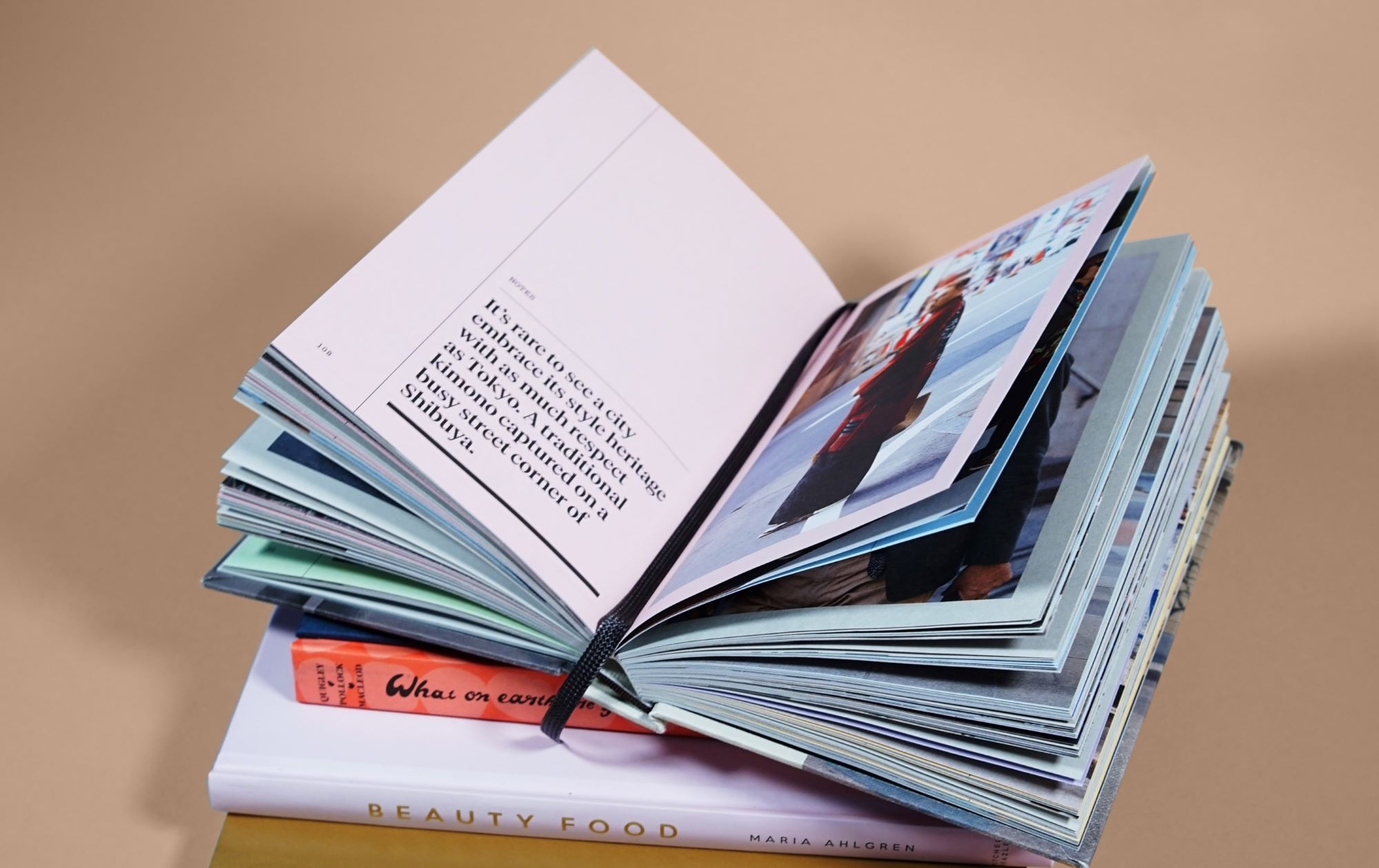
上製本は、加工方法の選択肢が多く、オリジナリティあふれる冊子に仕上げられる製本方法です。上製本ならではのこだわりポイントとして、花布やスピンといったオプション加工にも着目してみてください。
花布は、上製本を真上から見た時に、本文の背と背表紙の間の上下2箇所に貼られた小さな布です。本来は本の強度を高める目的で使用されていましたが、現在では装飾の意味合いも強くなってきています。
スピンは、上製本の本文の背に付いている紐のことで、読んでいる途中のページにはさんでしおりとして使うことができます。カラーバリエーションが多彩で、表紙の色やデザインに合わせて選ぶことで、ますます印象的な仕上がりになります。
また、ページ数が多くて厚い上製本の場合、ブックケースをセットにすることも可能。本を保護する機能的な面はもちろん、装飾としてさらに高級感を演出することができます。

CCG HONANDOでは、自社工場内で製本工程をすべて管理して製造し、上製本は社外協力会社と製造することが可能です。これまで積み重ねてきた品質管理のノウハウと知見を最大限に活かしながら、お客様にご満足いただけるベストなクオリティのものをご納品いたします。上製本をはじめ、さまざまな製本方法に対応していますので、冊子印刷でお悩みの方はいつでもお気軽にご相談ください。私たちCCG HONANDOがお悩みを解決し、お客様の事業を後押しする印刷物をご提案いたします。
各種お問い合わせ / 印刷のお見積もり・ご相談など
ご不明点ございましたらこちらよりお問い合わせくださいませ